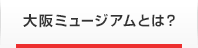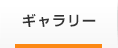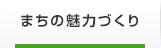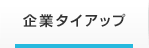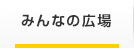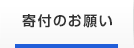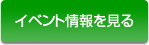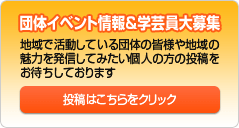最近の学芸員の投稿
 2015年2月26日
2015年2月26日学芸員投稿について
 2015年2月17日
2015年2月17日渡来人と高向玄理(古代の河内長野)
 2015年2月17日
2015年2月17日文化財の宝庫・河内長野市の天野山金剛寺の見学
 2015年2月17日
2015年2月17日かわちながのサロン@まちライブラリーNo1
 2015年2月9日
2015年2月9日河内長野市・下里の「九頭神(くずしん)」伝説
 2015年2月9日
2015年2月9日修理を終えた天野山金剛寺の多宝塔
最近のイベント情報(開催日順に表示)
学芸員の投稿
Update:
2013年10月08日
平成25年度の河内長野市「だんじり祭り」
学芸員の投稿
Update:
2013年10月08日
「河内長野の古墳時代」の展示会