現在の検索条件
-

髙林家住宅(たかばやしけじゅうたく)
髙林(たかばやし)家住宅は、御廟山古墳(ごびょうやまこふん)の南側にあります。白壁の土塀で囲まれた屋敷で、茅葺き屋根の主屋に土蔵や不動堂、稲荷社があり、敷地全体が江戸時代・近畿地方の庄屋の屋敷構えがよく残っています。1500年代後半の天正年間に建てられ、増改築によって座敷や玄関などが整えられ、18世紀終わり頃、現在の姿になったと伝えられています。重要文化財。
*現在も居宅として利用されていますので、外観からの見学をお願いします。 -

黒姫山古墳(くろひめやまこふん)
黒姫山古墳は、全長114m、前方部の幅65m、後円部の径64m、高さ11mの二段築成の前方後円墳で、百舌鳥古墳群と古市古墳群の中間に位置します。昭和22年(1947)に発掘調査が行われ、一基の古墳への副葬品量としては全国最多の鉄製甲冑などが出土し注目を集めました。古墳時代の中期に築造されたと考えられており、中世には砦としても利用されていたようです。
昭和32年(1957)、黒姫山古墳のもつ重要性から国の史跡に指定され(昭和53年、周庭帯部分を追加指定)、平成元年(1989)からは、国と府の補助を受けて、環境整備が実施されました。出土した大量の甲冑は、現在までに大半が保存処理を終え、M・Cみはら(堺市立みはら歴史博物館)でその一部を展示しています。 -

舟渡池公園(ふなといけこうえん)
美原区内で最も大きいため池である舟渡池のほとりにある公園です。池にはゴイサギやカルガモなど、一年を通してバードウォッチングを楽しむことができ、多くの人々の散策や憩いの場として利用されています。
-

本願寺堺別院(ほんがんじさかいべついん)
堺市内最大の木造建築で「北の御坊」とも呼ばれ、現在の本堂は1825年の再建されました。明治4年の廃藩置県後10年間堺県庁として使用後、浄土真宗本願寺派へ返還され堺県庁跡として府指定の史跡となっています。
足利義氏(よしうじ/1189-1254)の四男・道祐(どうゆう)が、本願寺三世覚如に帰依して建立したのが始まりとされています。文明8年(1476)、5世樫木屋道顕(かしきやどうけん)が本願寺八世蓬如を招き、その住居として現存している「信証院」を建てた。寛文3年(1663)には、十三世乗珍が寺地を西本願寺に寄進、以来別院となりました。
本堂・山門・鐘楼ほか、江戸時代の境内伽藍を伝える建築群は堺市指定有形文化財。 -

妙國寺(みょうこくじ)
1562年日蓮宗の日珖が開いたとされ、境内には、創建時に寄進された樹齢1000年を越す蘇鉄が、いまも生き続けています。高さ5m以上、大小120数本の幹枝を数える大木は、国の天然記念物です。
千利休寄贈の六地蔵燈籠や瓢型手水鉢がある日本唯一の「蘇鉄の枯山水」庭園、堺事件の土佐藩士切腹の地でも有名です。
かつて、織田信長がこの蘇鉄の見事さを気に入り、安土城へ移植させたところ、蘇鉄は毎夜「堺へかえろう、堺へかえろう」と泣いたといわれています。それを聞いた信長は、激怒して幹を切りつけると、蘇鉄は血を流して苦しんだため、元の妙国寺へ返したという伝説があります。 -

堺市役所21階展望ロビー(さかいしやくしょにじゅういっかいてんぼうろびー)
地上80m、堺市役所最上階で360度のパノラマ展望が楽しめる回廊式ロビーです。眼下には世界最大規模の前方後円墳・仁徳天皇陵古墳の全景をはじめ、堺の街並みが広がり、東に生駒・金剛山、西に六甲山なども一望できます。
21時まで開放しており、夜景観賞も楽しめます。 -
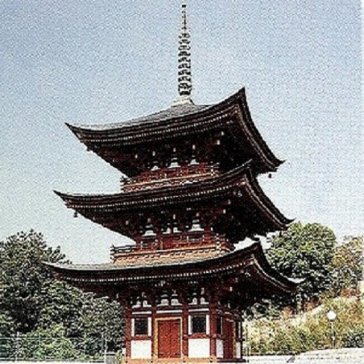
家原寺(えばらじ)
慶雲元年(704)、奈良時代の名僧行基が菩提寺として自らの生家を寺にしたのが始まりとされている名刹。山号の「一乗山」は、人が仏の心を学ぶ聖地、「家」は行基の生家、「原」は母親のお腹をそれぞれ表すもので、行基の活動の原点ともなった寺です。この名称が現在の地名にも残っています。
「智恵の文殊さん」と知られ、かつては、受験生がその願いを本堂に書いたことから別名「落書き寺」としても有名です。現在は祈願を書いたハンカチを本堂に貼り付けています。本堂の壁や柱がハンカチで埋め尽くされる姿は、毎年の風物詩。また、1月14、15日に行われる左義長祭りは「家原のとんど」として、知られています。 -

堺市博物館(さかいしはくぶつかん)
堺市博物館は、市制90周年記念事業として昭和55(1980)年に開館しました。生涯学習と市民文化の向上のため、堺市の歴史、美術、考古、民俗に関する博物館として、多くの資料を収集、保存、展示しています。
常設展示「百舌鳥古墳群と堺の歴史・文化」では、堺市の歴史を「古墳の時代」「中世の堺」「堺の産業・文化」そして「堺の宗教文化・堺市博物館の収蔵庫から」と、4つのコーナーに分けて展示。特別展や企画展などもあります。また、数多くある館蔵品のなかには、観音菩薩立像や漆塗太鼓形酒筒など、国の重要文化財に指定されている3点も含まれています。 -

堺 アルフォンス・ミュシャ館(堺市立文化館)(さかいあるふぉんす・みゅしゃかん さかいしりつぶんかかん )
アール・ヌーヴォー期に活躍した芸術家アルフォンス・ミュシャの作品を展示する美術館。ミュシャの初期から晩年期の作品を展示し、生涯にわたる創作活動を紹介しています。ミュシャの作品は、しなやかな曲線と美しい色彩が特徴で、チェコやビザンティンなどの装飾様式のほか、日本美術の要素も見られます。また、与謝野晶子や鉄幹が活躍した『明星』の挿絵に取り入れられるなど、日本にも大きな影響を及ぼしました。
-

ザビエル公園(ざびえるこうえん)
天文19年(1550年)に来堺したイエズス会の宣教師フランシスコ・ザビエルを手厚くもてなした豪商・日比屋了慶(ひびやりょうけい)の屋敷跡につくられた公園。昭和24年(1949年)ザビエル来航400年を記念して「ザビエル公園」と命名され、記念碑も設置されました。そのほか、園内には階段状の護岸や南蛮船をイメージした遊具があります。




